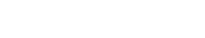流し雛は、子どもの健やかな成長を祈って「流し雛(びな)」を御手洗(みたらし)川に流し、無病息災を祈る古来からの神事です。 桟俵(さんだわら)にのせた雛人形に厄(やく)を移し、平安装束のお雛様に扮した男女が御手洗川に流します。
開催のご案内
流し雛神事は雨天の場合祭場を御手洗池より橋殿に変更となる可能性があります。
御手洗池での神事はございませんのでご注意下さい。
お知らせ


流し雛のながれ
10:30
橋殿で、お雛様に扮する女性の十二単の着付けが始まります。
着付けの説明も聞くことができます。



11:00
井上社(御手洗社)で神事が始まります。
神職によって祝詞(のりと)が奏上され流し雛が始まります。



◆流し雛では、平安装束を身につけた男女がまず御手洗川に流し雛を流します。


◆子どもたちが桟俵に乗せた雛人形を御手洗川に流して、無病息災を祈ります。
◆雨天場合中止、変更となる可能性があります。


◆芸舞妓さんたち3名が流し雛を行います。
◆雨天場合中止、変更となる可能性があります。

御神水を頂き神事を終えます(紙コップで無人の水飲み場で飲むか、有人の水飲み場で陶器の器で飲むか、2通りございます)



御神水を頂き神事を終えます(紙コップで無人の水飲み場で飲むか、有人の水飲み場で陶器の器で飲むか、2通りございます)


◆流し雛が終わり、子供達が「うれしいひなまつり」の曲を合唱します。
◆雨天場合中止、変更となる可能性があります。
◆そのあと、一般の参拝者が流し雛(有料)を流し、無病息災を祈願します。

御神水を頂き神事を終えます(紙コップで無人の水飲み場で飲むか、有人の水飲み場で陶器の器で飲むか、2通りございます)

井戸の上に祀られている末社の井上社、別名「御手洗社(みたらししゃ)」があります。
そこから湧き出る水が御手洗池・御手洗川となって、境内から糺の森へと流れていきます。
この御手洗池・御手洗川で流し雛が行われます。
御手洗社は水の流れを司り祓い浄めの女神である瀬織津姫命(せおりつひめのみこと)を祀っています。