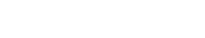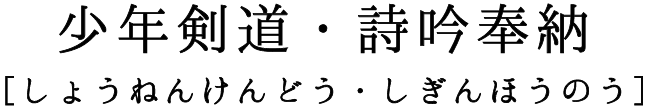毎年5月15日に行われる賀茂祭(葵祭)は今から約1500年前の(540~572)年、凶作に見舞われ飢餓疫病が蔓延した時に、欽明天皇が勅使を遣わされ、「賀茂の神」の祭礼を行ったのが起源とされています。下鴨、上賀茂両神社の例祭であり、天皇の御使いである勅使がご奉��仕になる「勅祭」です。古代には「祭」といえばこの賀茂祭(葵祭)を指す程、貴族社会に根差しておりました。現在でも、「祇園祭」「時代祭」と並んで「京都三大祭」の一つに数えられています。
賀茂祭は国家安泰を祈願するお祭りであり、このお祈りのため、5月の下鴨神社では多くの神事が行われます。

※斎王代御禊の儀は上賀茂神社と隔年で交代。令和7年は上賀茂神社にて斎行。


日にち
5月3日
場 所
糺の森の馬場(MapNo.45)
時 間
13:00頃〜 ※時間は変更になる場合あり。
一般の方の�ご見学
可能
お申し込み
観覧:無料。有料席有。申し込みは当日券のみ。当日正午より糺の森切芝にて受付予定
流鏑馬は「やぶさめ」、あるいは「やぼさめ」と読みます。また「矢伏射馬」とも書きます。公家や武家の狩装束を用いた射手(いて)が馬上から鏑矢を放って的を射る行事(走馬の儀)で、本祭に先立って行われ、葵祭シーズンの到来を告げます。
葵祭の行粧の安全を祈って行われる祓の神事です。 �糺の森の中(参道沿い)にある約400メートルの馬場を馬と駆け抜けながら、三カ所の的に矢を放つ様子は大迫力。 射手が射抜いた的は「当的」として、縁起物として授与されます。

日にち
5月4日 ※上賀茂神社と隔年で交代。令和7年は上賀茂神社にて斎行。
場 所
井上社前の御手洗池(MapNo.17)
時 間
神事は10:00〜 (斎王代が手を浸すのは11:00すぎ)
※時間は変更になる場合あり。
一般の方のご見学
可能
お申し込み
不要
斎王とは、平安時代から鎌倉時代に存在した、賀茂の神に御奉仕した未婚の内親王です。現在はその代理として、京都在住の一般の方から選ばれた女性が務めることから「斎王代」と呼ばれます。賀茂祭に先立ち、神社の水に手を浸し、身を清める禊(みそぎ)を行います。 青葉こもる神域で華やかな十二単の上に白い小忌衣[おみごろも]を召された斎王代、あどけない童女、小袿の命婦[みょうぶ]・女嬬[にょじゅう]・内侍[ないし]・女別当など五十余名の女人列が雅楽の流れる中、進む�様はまことに優美な王朝絵巻を彷彿とさせます。

日にち
5月4日
場 所
舞殿・橋殿
時 間
13:00〜 ※時間は変更になる場合あり。
一般の方のご見学
可能
お申し込み
不要
古武道奉納では賀茂祭に先だって、日本各所から外国人も交え、30を超える流派が参集、日頃の研鑽の成果が披露されます。
薙刀、剣術、柔術、居合をはじめ珍しい棒術や鎖鎌などの古武道を直接拝見できる貴重な機会です。

日にち
5月5日
場 所
本殿・舞殿
時 間
11:00〜
一般の方のご見学
可能
お申し込み
不要
弓矢を使って葵祭の沿道を清める魔除けの神事です。3日の流鏑馬に対して、地上で矢を射ることに由来しており、平安時代に宮中で行われていた「射礼[じゃらい]の儀」が始まりと伝えられています。
射手が弓を鳴らす「蟇目式[ひきめしき]」で四方の邪気を祓い鏑矢を「ヒョウ」と楼門の屋根を越えて飛ばす「屋越式[やごししき]」 、大きな的を射る「大的式[おおまとしき]」 、連続で矢を射る「百々手式[ももてしき]」が行われます。
この四式をもって「鳴弦蟇目神事[めいげんひきめしんじ]」と呼ばれ、賀茂祭(葵祭)の安全祈願とされています。

日にち
5月8日
場 所
本殿・舞殿
時 間
10:00〜
一般の方のご見学
可能
お申し込み
不要
葵祭を祝い、神の御心を和める神わいの行事として献茶祭が行われます。表、裏、武者小路の三千家家元が交替で奉仕します。当日は祝詞奏上の後、舞殿において家元の点前で濃茶と薄茶が点てられ、神前に奉献されます。副席や野点席、点心席なども設けられ、境内は和服姿の人々で華やかな雰囲気になります。令和7年は裏千家奉仕となります。

日にち
5月12日
場 所
下鴨神社〜御蔭山〜賀茂波爾神社〜下鴨神社
時 間
9:00〜行粧進発、12:00〜御蔭山の儀、
15:30行粧下鴨神社へ到着、16:00〜切芝神事
一般の方のご見学
次の神事のみ可能。
行粧・路次祭(賀茂波爾神社)・切芝神事
お申し込み
不要
比叡山山麓の御蔭山[みかげやま]には下鴨神社御祭神の荒御魂をお祀りする御蔭神社が鎮座しております。5月12日は御蔭神社にて新しく御神霊がお生まれになるとされており、この御神霊を本社へ迎える神事です。この祭は我が国最古の神幸列を残すものとされ、神馬上に御神霊を遷し、本社に迎える古代の信仰形態を今に伝える祭として有名です。 御陰祭も複数の神事で構成されています。
まず、下鴨神社舞殿にて、勧盃の儀[かんぱいのぎ]・樹下神事[じゅげしんじ]の後、神職・氏子などの行列(行粧[ぎょうしょう])が楼門より出発し、御蔭山まで巡行します。
御蔭山の御蔭神社へ行粧が到着すると、正午にお生まれになる御神霊をお遷しする儀式が斎行されます。
御神霊は行粧とともに山を下り、その後、賀茂波爾神社[かもはにじんじゃ](赤の宮)に至り、路次祭[ろじさい]が行われ、「還城楽[げんじょうらく]」という舞楽が奉納されます。
下鴨本通りの北部にて御神霊は神馬上にお遷りになり、下鴨本通りを南下し、下鴨神社に至ります。御本殿へ進む途中、糺の森切芝にて神馬の前で神を讃える歌が舞とともに奏されます(切芝神事)。 その後、御本殿へと進まれた後、御神霊は下鴨神社の御神霊と一体となり、力を高められます。

日にち
5月14日
場 所
鳥居〜本殿
時 間
10:00〜
一般の方のご見学
可能。
お申し込み
不要
葵祭の前日に、滋賀県大津市にある堅田(かたた)という地域から、琵琶湖で獲れた鮒を奉納する神事で、平安後期より続く行事です。
当日朝、供御人行列は堅田地区の伊豆神社・神田神社で祈祷を受けた後、地域を巡行し、バスで下鴨神社に到着します。
鮒の入った唐櫃や太鼓、里人など様々な衣装に扮した供御人の長い行列が、糺の森をとおり本殿まで向かう様子は、平安より続く人々の祈りの姿を感じることができます。15日の葵祭に供えられる鮒が奉納されます。

日にち
5月17日
場 所
舞殿
時 間
11:00〜
一般の方のご見学
可能。
お申し込み
不要
貞松斎米一馬いらいのゆかしい手振を伝える遠州宗家一門が、精魂こめて生花(木もの)を生け、当神社の神前に供えます。門弟の人々も参列して年に一度、賀茂の大神を慰める儀式です。

日にち
5月18日
場 所
舞殿
時 間
10:00〜
一般の方のご見学
可能。
お申し込み
不要
祭を締めくくる奉納神事で、神に煎茶(せんちゃ)を奉納します。 舞殿にて、小川流家元が白磁、白泥の道具を使って厳かに一煎を入れ、神職が西と東の両御祭神に献じます。

今から約550年前に将軍足利義政をはじめとする大名の前で行われた「糺河原勧進猿楽」を、賀茂御祖神社第34回式年遷宮に際し、550年ぶりに再興いたしました。賀茂御祖神社では、令和18年に第35回式年遷宮を迎えることから、その奉賛事業として例年5月の下旬に奉納されます。令和7年に10回目となる糺能では、遷宮にむけて、新作能《糺》が上演されます。


日にち
5月15日 ※15日が雨天の場合、行列は16日に順延。
場 所
京都御所〜下鴨神社〜上賀茂神社
時 間
10:30〜
※時間は変更になる場合あり。
一般の方のご見学
次の神事のみ可能。
路頭の儀・社頭の儀
お申し込み
不要。
平安王朝時代の古式の姿を今に残す賀茂祭。勅使、供奉者の衣冠、牛馬にいたるまで、全てを葵の葉でお飾りし、祭礼の後に神様の力の宿った葵が贈られたことから「葵祭」と呼ばれるようになったとされます。 「宮中の儀」「路頭の儀」「社頭の儀」の三つに分けて行われますが、よく知られているのが「路頭の儀[ろとうのぎ]」と称される葵祭のハイライトとなる都大路の行列。およそ1キロメートルの行列が平安貴族そのままの姿で、京都御所を出発し、優雅な列が市中の全行程8キロにわたる道筋を練り、下鴨神社へ至り、その後、上賀茂神社へと向かいます。
ポイント
上賀茂・下鴨両神社の例祭。「三勅祭」(勅祭=天皇の使者が派遣されて行われる祭)「賀茂祭・春日祭・石清水祭」の1つ。また、「祇園祭」「時代祭」と共に「京都三大祭」としても認知されております。
京都御所を出発し、下鴨・上賀茂の両神社へ向かう「路頭の儀」の行列は、斎王代や様々な所役の美しい装束が見もの。王朝文化が色濃く残る京都の伝統産業の技を感じることができます。
その優美な様子は、この国の祭り中の祭として『枕草子』にも称えられているほか、『源氏物語』の「車争い」の場面でも有名。およそ1500年もの長い間続く、日本を代表する祭礼です。
下鴨神社での神事

下鴨、上賀茂の両神社に、勅使が御幣物を供え、御祭文を奏上する「社頭の儀」に向かう道のりになります。 束帯姿の近衛使代や十二単の斎王代など、王朝絵巻さながらの装束や装飾が見もの。京都の伝統産業に支えられ職人技に磨かれた伝統が息づいています。
「路頭の儀」は大きく2つの行列があります。


勅使の役目をする近衛使代(このえつかいだい)を中心とするもの
検非違使などの警衛列・神様への供物などの幣物列・走り馬の列・勅使の列で構成されています。 この列の中心は、黒い束帯を着て飾馬に乗っている近衛使代(このえづかい)です。

検非違使志
(けびいしのさかん)

御幣櫃
(ごへいびつ)

牛車
(ぎっしゃ)


斎王代(さいおうだい)を中心とするとするもの
「斎王」は本来未婚の皇女であり、その代理である「斎王代」も十二単の姿で「御腰輿(およよ)」と呼ばれる輿に乗られています。斎王代列は基本的に女性で構成されます。

斎王代
(さいうだい)

騎女
(むなのりおんな)

命婦
(みょうぶ)

勅使が賀茂の神様のために御幣物を供え、御祭文を奏上します。 平安朝以来の古儀にしたがって、奉幣、舞楽、東游、牽馬などが行われます。社頭の儀の後には糺の森の馬場にて「走馬(そうめ)の儀」が行われ、数頭の馬が繰り返し疾走します。
「路頭の儀」のおもなルート

葵祭にちなんだ御朱印とお守りの授与
下鴨神社では、5月1日からの賀茂祭(葵祭)にちなみ、「四季守 葵」を授与致します。また、賀茂祭(葵祭)当日には「葵祭」と記載された限定の御朱印を授与致します。

写真は書置きのものになります。 帳面への押印も受け付けております。
※帳面へ押印の場合は葵桂の絵は入りません。
※デザインは予告なく変更となる場合がございます。

「四季守 葵」
令和7年度の仕様となります