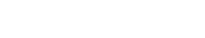明けましておめでとうございます
本年はおだやかに明けました
何よりと存じます
どうか好いお歳になりますようお祈り申し上げます
当お社にお参りいただくにあたり、古代は、参道が三筋ございました。
というのも当お社は大勢の皆様が一度にお参りできるように社殿構造がなりたっておりません。
一筋目として、古代は、烏の縄手(からすのなわて)と称する参道が糺の森の樹間をぬうように、枝々をくぐりぬけるようにして存在しました。
二筋目は、賀茂川と高野川の三角州に祀られていた葵祭の斎王様の唐崎社から、楼門東の屋形橋までの古馬塲の行幸路です。お馬さんが走る走路が表参道として、現在の家庭裁判所から朱橋(あけはし)まで道となっていました。現在の馬塲は、鎌倉時代からの馬塲です。
三筋目は、かつて山背国愛宕郡(やましろのくにおたぎのこうり)時代の出雲郷から賀茂川の出雲橋を渡る西参道でした。
御本宮の表参道には「御船」、西参道には「三本杉」、烏の縄手には「出雲路」と称する御手水舎があります。
それぞれに謂れがあり、「御舟」のものは、御生神事(みあれしんじ)の神事歌謡である古歌にその伝承が伝えられています。
一段 しもとゆう かつらきやまに ふるゆきの まなくときなく おもほゆるかな
『古今和歌集』収載
二段 やまとかも うみにあらしの こちふかは いづれのうらに みふねつなかむ
『新古今和歌集』収載巻十九、神祇歌、
鴨社の午の日(御生神事こと)謳い侍る歌と、伝承を伝えています。
日向の曽峰に御祭神が降臨され、浪速津から鴨川を遡り此の地に着かれたとの伝承を基に「御舟」を屋形としています。
西参道の「三本杉」は、古代の御生地として、この世とあの世の境目とされていました。その標として大木の杉の間が御生地の目印であったという伝承です。
「出雲路」は、鴨の地と出雲の境の標として古代の橋の石脚をくりぬき、水受けにしたと伝承をつたえています。
宮司 新木 直人